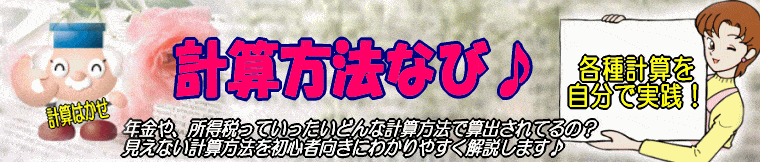計算方法なび♪では給与所得控除の控除計算がどのように算出されているのか?について初心者向きにイラストや図を用いてわかりやすく解説しております。
◆給与所得の計算方法なび♪(もくじ)
- ⇒給与所得控除とは?
- ⇒給与所得控除制度が導入された理由
- ⇒給与所得控除の最大のメリット
- ⇒給与所得控除の計算方法の計算式
- ⇒給与所得控除速算表
- ⇒お給料以外の形のもので給与所得とみなされるもの
- ⇒給与所得とみなされない手当や費用など
- ⇒給与所得控除計算例
- ⇒給与所得控除と基礎控除の適用
- ⇒給与の総額が65万円以下のケース
◆給与所得控除とは?
給与所得控除とはサラリーマンの職務上の必要経費に関して、「おおよその概算で経費額を算出した額」を、経費分として控除する制度です。
当然サラリーマンの場合、個々の違い、また業種によっても必要経費額は異なってきます。
しかし、現在の税制における給与所得控除では、全体のおおよその平均からパーセンテージを算出しております。
ですから、経済状況などによって、この給与所得控除のパーセンテージ割合が変更となる可能性もある点を事前に把握しておく必要があります。
この給与所得控除制度の簡易性、そして絶大な節税効果は個人事業主が「法人なり」をする最大の理由ともなり得る控除制度でもあります。
ここでは、このとてもありがたい控除制度である給与所得控除について初心者向きに解りやすく解説を加えていきますのでしっかり確認しておきましょう。
◆給与所得控除制度が導入された理由

仕事で使うバッグ・ビジネスシューズ・夏用、冬用、季節によって用意するスーツ、更には、ワイシャツ・ネクタイまで、これらは「サラリーマンが職務を遂行する上で」必要不可欠な経費じゃ。
これらの職務上必要となる経費は、家計とは別に、必要経費として扱うのはサラリーマンとして当然の権利じゃな。
しかし、現実的に全国のサラリーマンがこれらの必要経費を全て把握し、法律に基づく経費として計算するのは困難な事であるのは容易に推測できる。
そこで税法ではサラリーマンの為に、これらの基本的にかかるであろう経費を概算で計算する「給与所得控除」という制度を認めたのが給与所得控除制度の発祥の由来じゃ。
給与所得者であれば全員一律で控除が適用となる。
また、実際に帳簿をつけてみると、給与所得控除で設定されている控除額は実際にかかると想定される経費額よりもかなり大きい事に気づくはずじゃ。
給与所得控除の最大の利点は、その簡易性、そして控除枠の大きさであると言えるじゃろう。
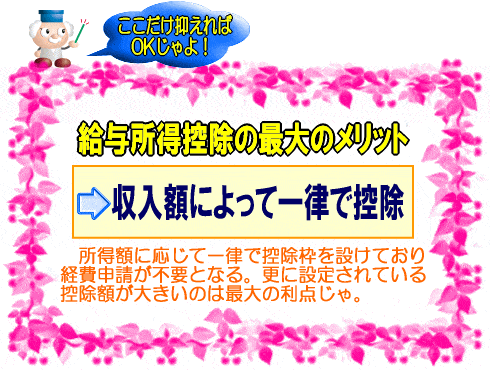
◆給与所得控除の計算方法の計算式
給与所得控除額の計算は以下の通りじゃ。
計算方式は所得が高くなるほど、職務に必要となる経費も高くなるという見解で定められておる。
その為、所得額が高いほど所得控除額もあがるという計算式じゃ。
一度自分の所得額を下記表に照らし合わせて計算し、自分の一体どの程度の給与所得控除が認められているのかを知っておきたいものじゃ。
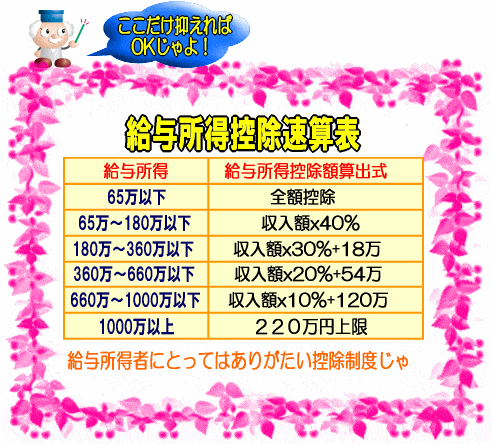
尚、平成28年度より1200万円を超える所得者に対する上限額230万円が設けられておったが、平成29年度より1000万円超は控除額一律220万円が上限となっておるので高額所得者の方は注意が必要じゃ。
◆お給料以外の形のもので給与所得とみなされるもの
給与所得とはサラリーマンの場合は、一般的に会社から職務の対価として支払われる「お給料」、役員の場合は「役員報酬」などが給与所得という項目に分類されます。
尚、法律的な給与所得の規定はもう少し幅が広くなっております。
イメージとしては毎月のお給料そのものが「給与所得の一種」という意味です。
これはお給料以外の収入に関しても給与所得として認定される項目が存在していることを意味しております。
尚、お給料以外の形で給与所得とみなされるものには以下のようなものがあります。
【社宅の自己負担額が相場の家賃額の半額以下の場合の不足部分の金額】
社宅の自己負担額が3万円
同規模・同グレードの賃貸相場は12万円
例えば、あなたの社宅の自己負担額が3万円。
しかし、同規模の同じようなグレードの賃貸相場の家賃額は12万円だったとします。
この場合は、12万円の半額は6万円。
この6万円と現行の家賃との差額3万円が給与所得とみなされます。
地域の家賃相場の半額よりも更に安い金額の設定に関しては手当の範囲を超える費用として給与扱いとみなすという事ですね。
※商品券や証券の支給を受けた場合
会社からお給料以外に、報酬もしくは手当てとして商品券や証券の支給を受けた場合は、その全額が給与所得扱いとなります。
但し、創業記念品や永年勤続記念品等に関しては一般常識の範囲内の金額であれば非課税扱いとみなされるものもあります。
※使途不明の交際費などの支給額
会社から交通費などの名目で経費を受け取ったとしても、その使途を明確に出来ない支給額分については給与所得扱いとなります。
この場合は、使途を説明出来るように、必ず「領収証」をもらうようにしておかなければいけません。
◆給与所得とみなされない手当や費用など
サラリーマンの場合は営業活動や企業の営利活動を行う際に必要となる手当や費用が会社から支給されるケースがあります。
これらの営業活動上の必要経費は給与所得扱いにはならず、非課税対象となりますのでしっかりと把握しておきましょう。
尚、給与所得とみなされない手当や費用には以下の様な課目が該当します。
| 【給与所得とみなされない手当や費用一覧】 | |
|---|---|
| 順不同 | 詳細 |
| ①通勤手当 | 1ヶ月に付き上限10万円まで |
| ②旅費手当 | 出張旅費、転勤・就職などの際の引越し費用、単身赴任者の一時帰宅費用 |
| ③社員食堂の食費 | 1ヶ月に付き上限3500円まで。但し月額7000円以上の負担を個人がしている場合に限り適用 |
| ④夜勤の食事代 | 1回の上限300円以下まで |
| ⑤宿日直料 | 1回の宿日直に付き上限4000円まで |
| ⑥学資金 | 社会通念上の適正範囲内 |
| ⑦記念品 | 創業記念、合併記念、増資記念などで上限1万円まで |
| ⑧永年勤続記念品 | 社会通念上の適正範囲内で勤続10年以上が対象 |
| ⑨社員割引 | 販売価格の70%以上の価格で購入した場合 |
| ⑩福利厚生施設 | 社会通念上の適正範囲内 |
| ⑪レクリエーション費 | 社会通念上の適正範囲内 |
◆給与所得控除計算例
給与所得控除額を計算するには、まず自分の「計算上の給与所得額」を確認することが必要です。
一般的なサラリーマンの給与収入は「給料」や「俸給」「賞与」などの形で支給されますが、この他にも給与所得としてみなされる収入、給与所得としてみなされない収入があることはここまでに解説してきた通りです。
では、ここからは具体的に給与所得控除額の計算方法についてチェックしていきましょう。
【給与所得額が年間450万円の場合と700万円の場合】
サラリーマンでお給料の総額が450万円のA氏場合と、700万円のB氏の場合を例に計算してみましょう。
【給与収入450万円のA氏の給与所得額の計算方法】
給与収入が450万円のA氏の場合は上記給与所得控除速算表を参照すると360~660万円の範囲に入ります。ですから
①450万円×20%=90万円
②90万円プラス54万円=144万円
となり、144万円が給与所得控除額となります。
課税対象となる「給与所得額」の算出では、450万円の給与収入から給与所得控除額を差し引き算出するだけですので
450万円-144万円=306万円
となり、306万円が課税対象となる給与所得額として認定されます。
【給与収入700万円のB氏の給与所得額の計算方法】
給与収入金額が700万円のB氏の場合は同じく上記表を参照すると660万円~1000万円以下の範囲に入ります。ですから
①700万円×10%=70万円
②70万円プラス120万円=190万円
となり、190万円が給与所得控除額となります。
課税対象となる「給与所得額」の算出では、同じく700万円の給与収入から給与所得控除額を差し引き算出するだけですので
700万円-190万円=510万円
となり、510万円が課税対象となる給与所得額として認定されます。
◆給与所得控除と基礎控除の適用
給与所得者の控除については、ここまでに解説してきた給与所得控除が基本となり、更に所得のある者全てが平等に控除を受けることが可能となる「基礎控除」があります。
この基礎控除の額は所得税と住民税で控除額が異なります。

前項の給与収入700万円のB氏の給与所得額の計算事例では、190万円の給与所得控除を受けて510万円となりましたが、ここから更に基礎控除38万円を加えて計算すると以下のようになります。
510万円-38万円(基礎控除)=472万円
実際に所得税・住民税の課税対象となる課税対象額を算出するには、この他にも社会保険料や、家族が居る場合は、配偶者控除、扶養控除、医療費控除等が更に加算されてベース額が計算される事になります。
所得税や住民税の計算はこのように「複数の控除の適用」を受けてベース金額が算出されているため、なぜこのような所得税になるのか?について初心者の方には解りづらくなっているのが実情です。
しかし、計算式と控除範囲を学習し、ひとつずつ計算を行なっていくと自分が収めるべき納税額を事前に自分で計算できるようになります。
◆社会保険料控除の計算方法はこちら
◆配偶者控除の計算方法についてはこちら
◆扶養控除の計算方法についてはこちら
◆給与の総額が65万円以下のケース
給与収入の総額が年間で65万円までの部分に関しては、その年度の収入金額分が全て給与所得控除額の対象となります。
ですから、65万円以下のケースでは給与所得控除により収入がゼロとみなされるため、個人にかかる住民税や所得税は発生しません。
但し、収入に関わらず発生する住民税の均等割は発生します。
尚、対象となる年度の総収入額が40万円であった場合は40万円が給与所得控除対象となり、40万円の収入に対して65万円の給与所得控除額が適用される事はありません。